近年は秘境駅が流行っているようだ。特に外国人からの人気が強く、海外のガイドブックに掲載されていたり、ツアーの目的地に秘境駅が組み込まれていることもあるようだ。この記事ではそのような秘境駅ブームを背景に、年100日旅行する東大生が秘境駅の意味や活路について考えてみる。
秘境駅とは
秘境駅についてGeminiに聞いてみると、以下のような答えが帰ってきた
秘境駅とは、人里離れた場所にあり、列車が停車しても乗降客がほとんどいないような駅のことです。周囲に民家や施設が少なく、アクセスが困難な場合が多いのが特徴です。その静かで独特な雰囲気が鉄道ファンに人気で、旅の目的地となることもあります。近年は廃止される駅も増え、その希少価値が高まっています。
だが、秘境駅についてはその絶対的な基準はない。ウィキペディアにおいては
「秘境駅(ひきょうえき)とは、鉄道駅のうち山奥や原野といった人里離れた場所(秘境)にあり、列車の停車本数が少なく、自動車や徒歩などでのアクセスも難しい駅を指す」
と紹介されている。
北浜駅(北海道)に訪れる多くの観光客
北海道道東にある釧網本線の駅「北浜駅」は秘境駅として知られる。「みにくいアヒルの子」や中国映画「狙った恋の落とし方。」など様々な映画やドラマで登場して以来、この駅を訪れる人は多くなっているそうだ。冬には流氷が見える駅としても有名だ。
この駅で10時40分に出発する釧路行きを逃せば、次は15時37分(これも夏だけの臨時)まで釧路方面の列車は来ない。私はこの約5時間を北浜駅周辺で過ごすことにした。
しばらくすると大型のバスが止まり、中から多くの訪日外国人の方々が降りてきた。狭い駅舎は突如として賑わいの場所となり、各々が写真撮影や見学などを行っていた。しかし15分ほどすると電車に乗ることはなくまたバスに乗って次の目的地へと向かっていった。そしてまた静かになった。
駅ノートにはたくさん文字が書かれていたが、そのほとんどは中国語であった。やはり中国映画のロケ地となったことは大きいのであろう。
その後も何人か自動車で北浜駅に立ち寄る人がいたが、ほとんどが10分くらいですぐに帰っていった。


下灘駅(愛媛県)は人が溢れかえる
予讃線(愛ある伊予灘線)にある下灘駅もかなり知名度の高い秘境駅だ。日本で海に一番近い駅と呼ばれたり、映画の舞台になったりしたこともあり、ご存知の方も多いだろう。松山駅から40分くらいとアクセスも比較的良い。アクセスの良い秘境駅というのは何とも違和感のある表現であるが。。。
伊予大洲駅・宇和島方面へ向かう予讃線の列車に乗った際にこの下灘駅を通過した。この駅の所属する予讃線は愛媛県と香川県を結ぶ主要路線であるが、伊予市駅から伊予大洲駅までの間は内子線を経由する新線が並行しており、特急などの多くの列車は新線を経由する。そのため下灘駅は2時間に一本、上下線合わせても1時間一本ほどしか来ない。このような駅へ向かう列車であるが、松山駅からの列車はほぼ満席である。そして案の定、下灘駅でほぼ全ての旅客が降りていった。秘境駅と呼ばれる駅は、人で溢れかえっていた。

糠南駅(北海道)へ行ってみる
北海道の宗谷本線の北側にある糠南駅も秘境駅として有名だ。駅舎には物置があり、乗客はその中で待つことができる。トイレは設置されておらず、徒歩25分のところにある生涯学習センターを利用することになっているようだ。そしてなんとこの駅に止まる列車は一日3往復のみだ。しかしこの駅の所在する幌延町では駅を活用した町おこしに取り組んでいることもあり、1日の平均利用者は0人でもこの駅は存続している。またこの駅ではクリスマスイブに鉄道ファンによるクリスマスイベントが行われることでも知られる。
私がこの糠南駅を訪れた際、乗降客はやはりゼロであった。付近には見渡す限り何もなく、人の気配も皆無だ。日によっては何人か自動車で訪れる人もいるらしい。
糠南駅をモチーフにした「ぬかにゃん」というキャラクターがおり、付近の店でぬかにゃんグッズを買うこともできる。

秘境駅と地域の潜在価値
このような秘境駅に共通する考え方は「住民が当たり前だと思っていたものが、住民以外の人にとって価値があった」ということであろう。誰も使わない駅や当然のようにそこに存在していた駅が、外部の人にとっては珍しいものとして映ったのである。これが観光開発において非常に重要な視点ではないだろうか。これまで多くの地域で観光協会などを設置し自分たちの観光地を研究したり、イベントを実施したりしてきたであろう。しかしそこに、観光客の目線が不足していた可能性は否定できないのではないだろうか。一方近年は地域おこし協力隊や都市の学生との交流などにより、その目線が含まれつつあるとも言えるだろう。
そしてもう一つ重要なのが、「列車に乗り降りする場所」としての駅の役割ではなく、「景色をみる場所」「非日常を感じる場所」としての駅に観光客が魅力を感じているということである。ある観光資源を辞書通りのものとして捉えるのではなく、複数の切り口で捉えることが、観光にとっては重要なのではないだろうか。
スーパーを観光地として捉える記事も公開しているのでぜひご覧ください
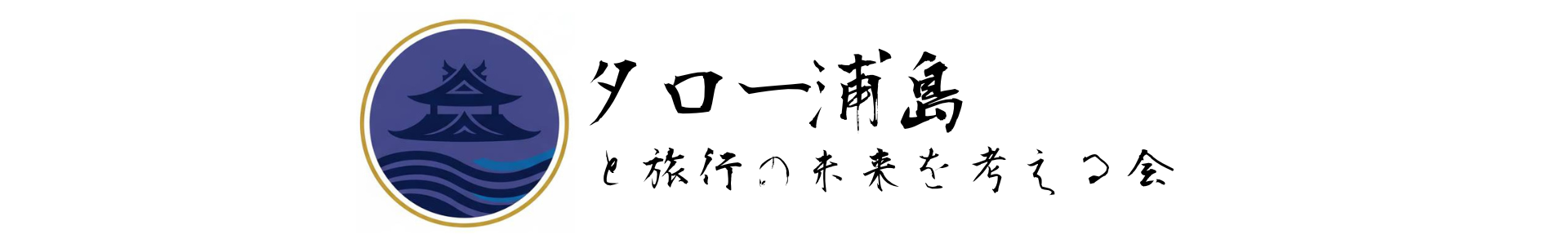




コメント