みなさんは大分県の中津市に行ったことがあるだろうか。中津は唐揚げが有名な街として知られ、有名な唐揚げ店が数多く存在する。中津からあげという名前は祭りの屋台などで見かけたことがある人も多いだろう。この記事では日本一周を3度実施した東大生が、地域活性化の観点から中津からあげのブームを紐解いていく
中津からあげとは
中津からあげは大分県中津市のご当地からあげである。中津はからあげの聖地ともされ、町中にからあげの専門店が多数立地している。中津では唐揚げ店が強すぎて、大手のフライドチキンチェーンが撤退を余儀なくされたという噂もある。そんな中津の唐揚げ専門店では、揚げる前に肉の重さを指定する。その後店員が揚げ、揚げたてを持ち帰ったりその場で食べたりするというスタイルだ。そのため中津のからあげ店では少々待たされることが多い。もちろん、待った分、味も格別である。
中津からあげは、今や限られた人しか名乗ってはいけないことになっている。中津商工会議所が「中津からあげ」を地域団体商標として商標を所持しているのだ。中津からあげを名乗るためには、以下の5点を満たす必要がある
◇「中津からあげ」使用条件◇(全て満たさなければなりません)
(1)中津商工会議所会員
(2)商品は「鶏肉をしょうが、ニンニクを基本とし醤油味または塩味を付加した独自の調味液に浸漬した後、油で揚げたからあげ」
(3)使用する鶏肉は100%国産鶏
(4)調味液は市販のものではなく各店舗で独自に作製
(5)中津市内に本店を構える事業所
引用:中津商工会議所ホームページ
このような要件を設けることによって、地域のブランドの保護と発展を促しているのだ。

中津の唐揚げのルーツ
大分における唐揚げの発祥自体は、隣接する宇佐市であると言われている。その後徐々に中津市にも進出してきたという形だ。1970年に開業した「森山からあげ店(現総本家もり山)」が中津における最初のからあげ専門店であると言われている。
中津市にはそれ以前から養鶏場が多く立地しており、鶏肉が入手しやすい地域であった。これが中津で唐揚げが広まった理由の一つではないかと言われている。実際、唐揚げ店が多くできる以前から、鶏の消費量は多い地域だったようだ。

中津の唐揚げが観光と結びつくまで
今でこそ大分県や中津市のガイドブックを開けば必ずといっていいほど紹介される中津のからあげであるが、「中津からあげ」が最初に名乗られたのは2003年頃であると言われ、有名になったのは意外に最近である。それ以前はどちらかというとローカル向けで、地元の人たちの食卓の一品としての要素が強かったらしい。その後、大分県北部には唐揚げ屋さんがたくさんあるらしいという噂が徐々に全国に広まり、メディアの取材なども増えた。中津の唐揚げ店をめがけて観光客が訪れるようになったのだ。

中津の唐揚げと地方創生の視点
中津の唐揚げのブームを辿っていくと、中津市が最初に唐揚げを積極的に発信したというよりは、外部の人たちがその珍しさに気づいたことで観光客が増えた、という流れが見えてくる。中津の人たちは日常の中にからあげ専門店があり、特に珍しいものであるとは考えていなかったであろう。しかし、中津市を訪れた外部の人にとってはそれが珍しいものであったり、魅力的なものであったりしたのである。
ここから学べるのは、「住んでいる人が当たり前だと思っていたものが、実は住民以外の人にとって価値の感じるものであるということがある」ということである。ここでは中津の例をあげたが、私がこれまで訪れたまちの中には、小学校の上履きとして生徒が草履を履いているまちや、ハエが信じられないくらい大量に飛んでいる街など、特殊なまちが多くある。その全てが魅力であるとは言えないが、魅せ方やアピールの仕方によってはその町のPRにつながるのではないだろうか。「上履きが草履のまち」「ハエが多い街」と調べようとした人が仮にいるのであれば、そのまちには潜在価値があると言えるだろう。しかしそういった街でもやはり住んでいる人は、珍しいことだとは感じていないのである。
観光開発のやり方について考える
現在の各市町村の現状を見てみると、各自治体ごとに独自の観光協会を作り、自分の町の観光スポットやルート、魅力などをを研究している。しかし、上の事例を見ればわかる通り、観光開発においては「訪れる側」の視点が必要不可欠なのである。自分の地域を自分たちでブランディングすると、本来注目すべき潜在的な魅力を見逃してしまう可能性がある。そこで私は「観光協会シャッフル」という手法を提案したい。たとえば北海道帯広市の観光協会が和歌山県串本町の観光を考えるのである。そして串本町の観光協会が帯広市の観光を考える。住人が気づかなかった「何か」に気づける予感がしないだろうか。なお、近年の市町村合併により、このような現象が部分的に発生している地域もあるようである。
そして、観光協会のみならず、旅行業界こそが地域の潜在価値を見出す場として機能しなければならないと考えている。ツアーの企画や相談などにおいて、隠れた魅力を旅行者に提供し広げていく役割があるだろう。需要ベースで旅行を作っていくという姿勢も企業としては大切であるが、旅行の将来を担う立場として発掘の段階を忘れてはならないだろう。
これからの観光は「よそもの目線」をより意識したものとなるべきではないだろうか。
最後までご覧いただきありがとうございました!
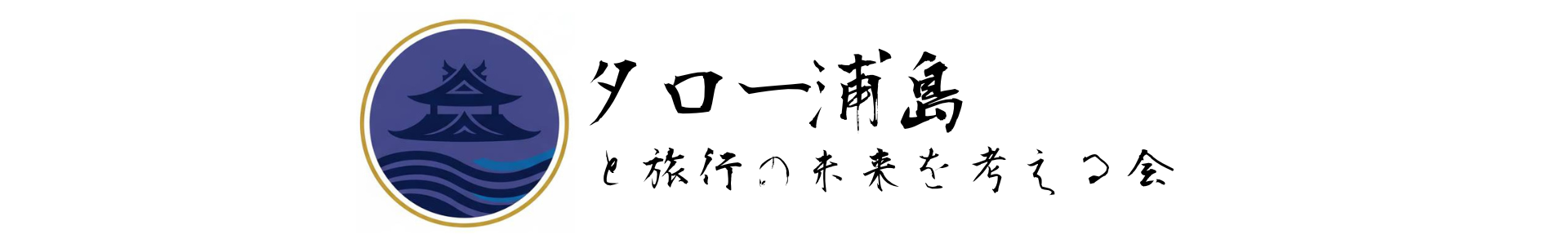



コメント