1987年、日本国有鉄道が分割民営化され、日本には6つの旅客鉄道会社(JR北海道・JR東日本・JR東海・JR西日本・JR四国・JR九州)と1つの貨物鉄道会社(JR貨物)が誕生した。それがJRである。しかし、JRの名がつくのはこの7つだけではない。実はあと2つあるのだ。それが鉄道総合技術研究所(JR総研・鉄道総研)と、鉄道情報システム株式会社(JRシステム)だ。今回は一つ目の鉄道総合技術研究所について深ぼっていく。
鉄道総合技術研究所(JR総研)とは?
鉄道総合技術研究所は、鉄道技術の研究開発を行う機関である。鉄道技術や鉄道労働科学に関する研究開発や調査、重大事故の調査などを主に行っている。この機関が他のJRグループと大きく異なるのは、株式会社ではなく公益財団法人であるという点だ。公益財団法人は公益事業を行う法人であり、財産そのものの集まりのことを言う。その財産を使って公益事業を行っていくのだ。鉄道総合技術研究所はJRグループの鉄道7社(北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州・貨物)が負担金を支出することによって運営されている。

JR総研の前身「鉄道技術研究所」
かつて日本国有鉄道には鉄道技術研究所があった。この機関では高速鉄道(新幹線)の研究や、リニアモーターカーの研究、無線列車制御システムの開発などを行っていた。日本の高度で安心な鉄道技術の研究開発を支えてきた機関だ。他にも国鉄には本社が持っていた技術開発部門や、鉄道労働科学研究所などがあった。これらの機関が国鉄の分割民営化の際に鉄道総合研究所(JR総研)に引き継がれたのだ。

JR総研が所有する研究所
鉄道総合技術研究所は業務遂行のために複数の研究所が存在する。現在は国立(くにたち)にある研究所をはじめ、米原にある風洞技術センター、南魚沼市にある塩沢雪害防止実験所、日野市にある日野土木研究所、村上市にある勝木塩害試験場の5つが存在する。国立の研究所には構内に線路が敷かれ、JR総研の車両が走行試験をすることもある、非常に大きな研究所だ。研究所では時々見学会が行われており、研究の現場を見られる機会が提供されている。
前身の国鉄鉄道技術研究所は、列車を脱線させまくる実験を行っていた狩勝実験線など、他にも多くの試験所を保有していたが、次第に閉鎖されていったので、今は5つのみである。

JR総研が所有する鉄道車両
JR総研は研究のために鉄道車両を保有している。かつて都心の通勤車両として活躍したディーゼル車のキハ30形式はその一つで、かつて八高線で使用されていた車両を現在も使用している。空転防止のための技術などを研究しているそうだ。
また、R291という試験車も保有している。画像は著作権の関係で載せることができないが、JR西日本の233系にそっくりな見た目である。燃料電池車両の実験や、信号設備等の実験にも使用しているそうだ。
JR総研が行っている研究
超電導き電システム
鉄道総合技術研究所ではさまざまな研究を行っており、その研究成果が時々ニュースなどで紹介されることもある。たとえば、超電導き電システムを使用することで送電時の電力損失を防止する技術が研究され、2025年3月からは中央東線の営業線区間において実証実験が行われている。
自立型列車運行制御システム
他に「自立型列車運行制御システム」と呼ばれるものもある。車両が自動で運行判断をしたり、支障物を確認したり、車上から転轍機や踏切を操作したりする技術で、将来の自動運転なども見越した技術開発を行っている。

高速パンタグラフ試験
電車の上についている集電装置「パンタグラフ」に関する技術の研究なども行われている。トロリー線の高さに合わせてパンタグラフが伸び縮みする仕組みとなっているが、その反応が遅いと離線が多くなってしまう。パンタグラフの架線への追従性能を測ったり、また流せる電流の大きさを計測したりする実験の映像が公開されていた。映像では時速360kmの場合を試験しているそうだ。最大時速500kmまで実験することができるらしい。

可動式ホーム柵支持部の設計法
近年設置される場所が増えている可動式ホーム柵に関する研究も行われていた。可動式ホーム柵自体もある程度重量のあるもので、かつ旅客がホーム柵を押したり、風が当たったりといったさまざまな要因があるため、その支持構造物はよく考えなければならないのだ。このような構造物に関する研究も多数行われている。

バラストに関する研究
鉄道の線路の下に敷かれている石をバラストと呼ぶ。この石は列車の揺れを抑えたり、騒音を防止したりする効果があるが、時間がたつにつれて石は砕けていく。劣化状態を測る方法として、これまでは目視による方法が取られていたが、掘り返したりするのは大変な上、定量的な判断が難しかったそうだ。そこでバラストの間を通る音の透過率で判断する方法が検討された。

まとめ
以上で見てきたように、JR総研(鉄道総合科学研究所)が日本の高い鉄道技術を支えていることがわかる。元をたどれば、新幹線も、リニア新幹線技術も、振り子式車体も、JR総研や鉄道総合研究所が行ってきたのだ。普段、列車に乗る際にあまり意識することのない会社かもしれないが、JR総研への感謝も忘れないようにしなければと感じたところである。最後までご覧いただきありがとうございました。
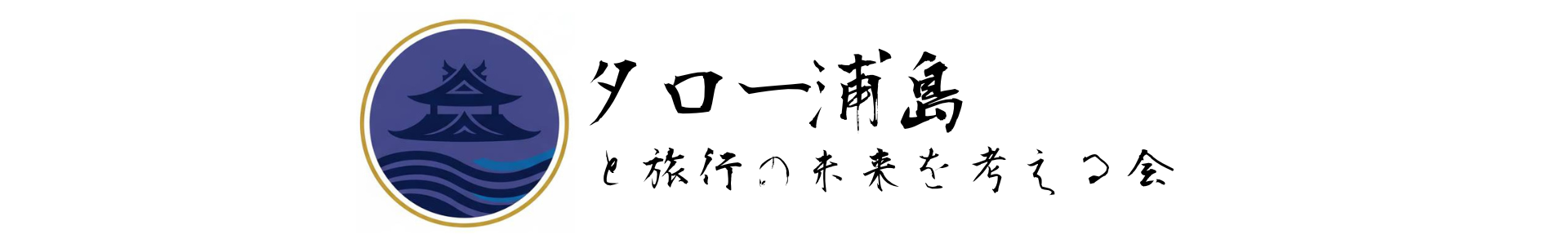



コメント