日本はインバウンドの観光客が数年前に比べると大きく増加した。中でも中国や台湾、韓国などのアジア地域からの観光客が多い。そしてニュースを見ると「中国では大型連休で国民が大移動」といったものを見ることが多い。この記事では中国の休暇事情と、中国人観光客が増えるタイミングについて紹介する。また観光客の経済的側面と、生じている問題についても紹介する。
中国の休暇事情
中国には、元旦(1日)、春節(3連休)、清明節(1日)、労働節(1日)、端午節(1日)、中秋節(1日)、国慶節(3連休)の7種類・計11日の祝日が存在する。逆に言えばこれだけしか祝日が存在しない。ではなぜ中国では大型連休が多いイメージがあるのだろうか。実は中国ではこれらの祝日の前後に休みを設け、土日を繋げて大型連休にするということが行われているのだ。その結果、実際の休みの日数は以下のようになる。なお休みの日数は日本のゴールデンウィークの日数が年により異なるように、中国でも年によりやや違いがる。ここでは2025年の休みの予定を示す。
| 春節 | 8連休 |
| 清明節 | 3連休 |
| 労働節 | 5連休 |
| 端午節 | 3連休 |
| 中秋節・国慶節 | 2025年は2つ接続で8連休 |
だが、この仕組みであると、本来の祝日+土日の日数よりも労働日数が減少することになってしまう。そのため、前後にある土日に出勤をするのだ。いわば土日をずらすような形で連休を作り出している。
多くの国民が一定期間に集中して移動するという点は日本にも共通する部分がある。ゴールデンウィークやお盆・正月をイメージするとわかりやすい。逆に欧米では有給を使って各々のタイミングでバカンスを楽しむというスタイルが主流だ。各国の休みの違いを見てみると面白い。

観光客が特に増える「春節」「国慶節」
例年中国において、春節や国慶節の際は7日前後の連休が設けられる。この二つのタイミングで特に中国人観光客が世界的に増加するのだ。2025年2月の春節の際に日本に訪れた中国人観光客は述べ98万人。2024年に来日した中国人の数が698万人なので、かなりの割合が春節や国慶節などのタイミングで訪れていることがわかる。観光サービスに関わる人たちや百貨店などは、このタイミングを狙ってイベントやキャンペーンを行うのだ。
この記事を作成している10月1日はちょうど国慶節真っ只中である。東大駒場キャンパスのまわりでも、特に渋谷駅周辺では多くの中国人観光客を見かける。2025年の国慶節では、日本が一番人気だそうだ。

経済の視点から見た中国人観光客
インバウンド全体の傾向
観光庁が発表している「インバウンド消費動向調査(2025年4-6月期)」を参考にすると、訪日外国人が消費した額は2.5兆円程度であるとわかる。そしてそのうち20%に当たる0.5兆円は中国人観光客による消費である。台湾・香港も含めると、40%近くまで達する。日本のGDPの約1%はインバウンド客による消費が占めていることを踏まえれば、観光は重要なセクターであることが分かる。
中国人観光客の傾向
そのような中国人観光客の消費総額は前年比で15%ほど上昇している。しかし、データを読み進めると、一人当たりの消費額は前年比で14.2%減少している。その代わり、客数が36.2%も増加しているので、その掛け算で求められる消費総額は結果的に上昇しているという形だ。1人あたりの消費額が減っている背景としては、中国経済の不況が挙げられる。不動産不況に始まり、コロナ以降の購買意欲の持ち直しに難があるなど、中国経済は厳しい状況にある。これにより失業率の増加も起こっているそうだ。このような事情もあってか、かつてのようにみんなが「爆買い」するような時代ではなく、物を慎重に選んで買う傾向が表れているらしい。
今後考えられること
ここ数年は1人あたりの消費額が減っても、客数が大幅に伸びているため観光地の経済的な潤いはある程度維持されると考えられるが、客数の伸びもいずれは限界が来ると考えられる。中国経済の動向によっては日本の観光地に小さくない打撃が与えられるだろう。観光サービスに関係するものが求められるのは、東アジア地域への過度な観光客依存から脱却し多角化することであると同時に、日本国内の日本人による需要も蔑ろにしないことではないだろうか。また、海外の人たちにとって「安いから買う」といった以上の付加価値を提供していくことも求められるだろう。「安く旅行したい」から「日本でお金を使いたい」のマインドへシフトしていく工夫が必要だ。

今年の国慶節と、さまざまな課題
今年の国慶節は映画の聖地巡礼なども流行っているようである。コンテンツ産業が国内の他の消費に繋がっていることは注目すべきだ。これまであまり観光客がいなかったような場所にも人が来る可能性がある。
もちろん、観光客が増えるということはそれなりに弊害も発生しうることだ。奈良公園の鹿が蹴られたり殴られたりしているということがネット上などで問題視されているが、観光客と地域・伝統・文化の繋がりのバランスはよく考えなければならない。「マナーを知らない人は来るな」と言うのは簡単であるが、日本経済の現状・地域経済の現状を鑑みると、なかなかそう短絡的な話でもない。日本人自身も、他国を観光した場合に、知らないところでその国のマナーに違反している可能性もある。大切なのは、まずお互いに理解する機会や理解しようとする姿勢ではないだろうか。その上でいかに伝統を維持しながら経済的利益を最大化させるのかを考えていかなければならないのだ。
最後までご覧いただきありがとうございました。
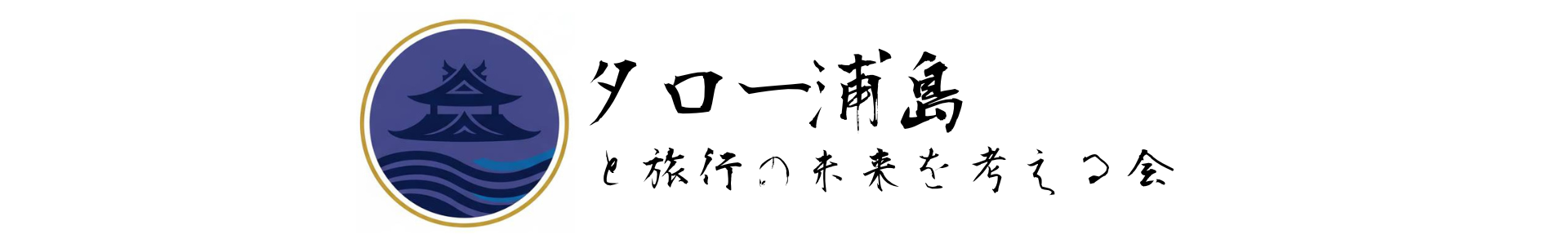



コメント