みなさんは徳島県名物といえば何を思い浮かべるだろうか。今回は美馬郡つるぎ町の名産「半田そうめん」を紹介する。名前だけ見れば普通のそうめんのようだが、実はこのそうめんは普通とは少し異なっている。今回は気候や法律の目線も踏まえて、日本一周を3回実施した東大生が紹介する。
半田そうめんとは
半田そうめんは、徳島県美馬郡つるぎ町に伝わる素麺を指す。このそうめんの特徴はなんといってもその太さとコシの強さだ。「舌の上で麺がはねる」とも言われる。実際に私も徳島県を訪れた際に食べたが、まるでうどんやひやむぎのような感覚である。実はこの点がこの後のパートで重要となる。半田そうめんは、もとは奈良県名産の三輪素麺の技術が、江戸時代に伝わったことが始まりであるとされている。吉野川の船頭たちが持ち込んだようだ。

素麺づくりが盛んな理由
徳島県つるぎ町(旧半田町)は、剣山(つるぎさん)と吉野川に挟まれた地域にある。この地域は四国三郎という呼称でも知られる吉野川から、肥沃な土壌と綺麗な水が豊富に供給される。また四国山地の北側に属し、いわゆる瀬戸内海式気候と呼ばれる乾燥地帯であり、香川県でうどんが有名であるということからもわかるとおり、四国北部全体でそうめんの原料となる小麦の生産が盛んなのだ。
また、素麺を作る工程の中で麺を干す作業がある。小麦生産の条件に加え、山間の地形で冷たい風が通りぬけることも、素麺づくりが行われる理由と言われている。

乾めん類品質表示基準について
ここで法律の話に移る。日本国においては、内閣府令で定める「食品表示基準」内の「乾めん類品質表示基準」において、麺の直径が1.3mm未満のものを「そうめん」、1.3mm以上1.7mm未満のものを「ひやむぎ」、1.7mm以上のものを「うどん」と呼ぶことが定められている。この表示基準に違反した場合、行政処分が行われる。従わなければ、個人の場合で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される。また法人であれば1億円以下の罰金が科される。
そこで太い素麺「半田そうめん」に出会った私は、半田そうめんの太さを調べることにした。小野製麺のサイトによると、半田そうめんの太さは直径1.4mmから1.6mmであるそうだ。品質表示基準に沿って考えると、半田そうめんは「ひやむぎ」である。
https://www.handamen.com/about
なぜ半田そうめんは食品表示基準の違反ではないのか
では半田そうめんを作っている業者は、組織的犯罪者なのかという話になるが、もちろんそんなことはない。現行の2016年に施行された内閣府令の食品表示基準は、かつての「日本農林規格」を踏襲したものとなっている。その日本農林規格では、半田そうめんは伝統などを考慮して、半田地区内で作られたものに限り特例で「そうめん」の呼称が認められていたようだ。また2000年施行の日本農林規格においては、機械生産ではなく手延べであれば1.7mm未満のものを「手延べそうめん」「手延べひやむぎ」のどちらの呼称でも良いこととなっている。半田そうめんは手延べ素麺であるから、1.6mmあってもそうめんを名乗っても良いのだ。
半田そうめんを食べてみた!
半田そうめんは徳島県内の郷土料理店などで食べることができる。徳島県を出ると出会う難易度が格段に上がるので、ぜひ徳島へ行った際には食べてみるのがおすすめだ。
私は阿波池田駅近くの飲食店で半田そうめんをいただいた。

そうめんといえば、冷やしてつゆにつけて食べるイメージがある。半田そうめんもこの食べ方で食べられるのだが、コシが強いということもあり、温かい状態で「にゅうめん」のような形で食べられることも多い。
私が行った店では、かけうどんを冷やしたような状態のものが提供された。写真を見ればわかる通り、まさにひやむぎのようである。だがひやむぎのもちっとした食感と、そうめんのつるっとした食感の中間くらいのイメージで、独特な感じだ。この店では徳島名産のすだちも乗っていたので、徳島県を存分に味わえる一品であった。
まとめ
今回は半田そうめんを、気候や法律などの側面から紹介しました。ぜひみなさんも半田そうめんを実際に食べてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。

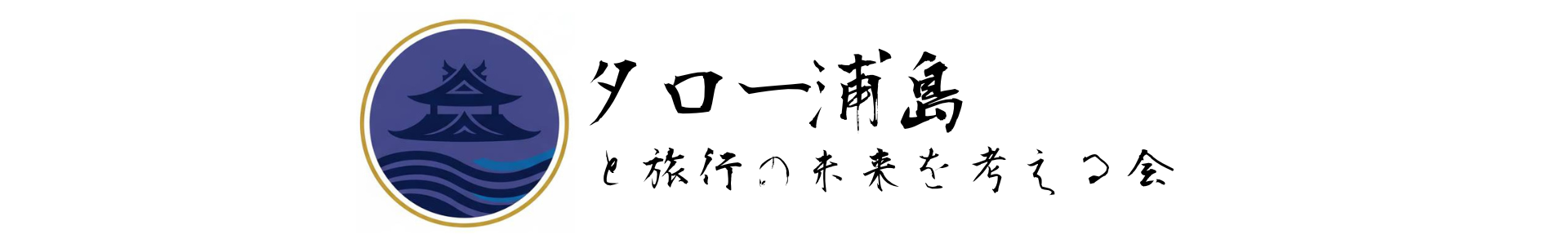



コメント